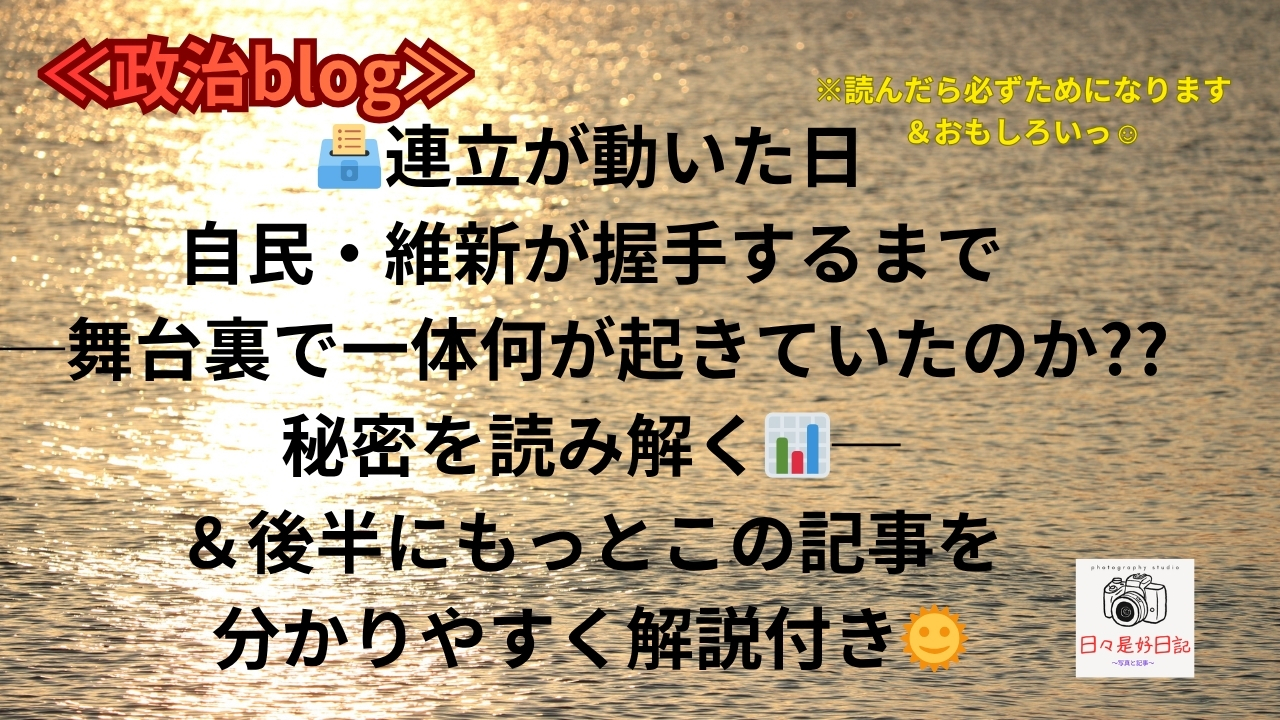
はじめに
10月20日、報道各社が「自民党・維新が連立政権合意に至った」と一斉に報じました。
政界再編の可能性を示す大きな変化です。
実際には、この合意に至るまでには、選挙の結果、議席数の変化、政策要求のすり合わせ、さらに既存政党間の駆け引き・亀裂が複雑に絡んでいました。
この記事では、
- 「なぜ維新が自民と連立を組むことになったのか」
- 「なぜ、従来の連立パートナーであった 公明党 が離脱したのか」
- 「他の野党(立憲民主党・国民民主党・参政党)との模索が不決着に終わった様相」
などを、時系列・人間ドラマ・政策の観点から掘りさげていきます。
内容的に少し難しく、政治チックになってしまっているため、専門的かもしれません。
そのため、後ほど後半に、素人でもわかる政治解説コーナー(コラムみたいなもの)を作りましたので、ぜひご覧ください。
少し難しい記事の後に、解説みたいなのが後半記事にあり、分かりやすく育てました。
もう一度復習の意味でも、じっくりご覧いただけるとありがたいです。
では、はじめます。。。
背景:議席構成と「数の論理」
まず、なぜ“連立”が必要になったのか──その鍵は「議席数」と「政策実行力」の二つです。
- 参議院・衆議院で、与党側(自民+公明)が安定した議席数を確保できなくなってきた、というのが出発点です。例えば、2025年の参院選報道では「衆院で与党が過半数割れとなれば、連立の枠組み拡大・他党との協調が現実味を帯びる」と指摘されています。
- 維新は以前から「自民との連立を排除しない」という意向を示していました。例えば、2024年5月24日の記事で、維新代表・馬場伸幸氏が「自民党との連立政権に参加する可能性」について「他党との協力には、連立入り・閣外協力・パーシャル連携など様々な形がある」と語っていました。
この発言は「維新としても、地域基盤+政策実現のためには、選択肢を閉じていない」ということを意味していました。 - また、報道では「もし“自公維”という政権が誕生したら……経済政策・企業活動にどのような影響があるか」という分析も出ており、政権基盤の変化が経済界からも想定されていました。
つまり、自民党側としても「与党単独+公明だけ」という枠組みでは将来不安」という認識があり、
維新側としても「政策実現/議席影響力」を得るために“自民との協力”を視野に入れていた、というのがまず一つの背景です。
維新が連立参画を選んだ理由
では、なぜ維新が最終的に自民との“連立・協力”に舵を取ったのか。以下、複数の要素があります。
1. 政策の接近・理念的な共通項
維新と自民には、ある程度の政策・価値観の重なりが指摘されています。たとえば、報道では「憲法改正」「安全保障の強化」「地方分権・行政改革」などのテーマで維新が主張してきた項目が、自民側とも接点があるとされてきました。
維新の党綱領においても「個人自立・地方自立・国家自立」「政府組織改革」「道州制」などが打ち出されており、これらが自民政権の中で一定の張りとなるテーマでもあります。
そのため、維新として「政策実現できる可能性があるパートナー=自民」という見立てを持ったことは、自然と言えます。
2. 議席の現実と“実績づくり”の必要性
維新としては「地方政党から全国政党へ」の展開を進めてきたものの、政策を国政の場で実行に移すためには与党/協力関係を確保せざるを得ないという現実があります。報道でも「維新が先行して与党と協議・合意に動いた」ことが指摘されています。
また、維新内部には「与党の中に入らなければ、政策は口だけで終わる」という焦りもあったようです。さらに、ある解説では「維新が入閣しない“閣外協力”方式を選んだのは、自らの“カード”として後々使えるから」という見方も出ています。
つまり、維新としては「今すぐに大きなポストを取る/政権に入る」よりも「政策協議の中で有利条件を引き出し、将来に備える」実利主義的な判断をした可能性があります。
3. 自民側からの“要請”とタイミング
自民党側からも、維新という比較的若く活力がある右派・改革派政党をパートナーに据えたいという思惑があったようです。特に、従来の連立パートナーであった公明党との間で亀裂が深まっていた時期に、維新を“連立/協力先”として打診する機会が出てきたという分析もあります。 選挙ドットコム
維新がタイミングよく“待機”していたとも言えます。つまり、「将来、枠組みが変わるならば自民との連携も排除しない」という姿勢を維新が示していたことが、今回の合意に至った下地になりました。
4. 地方基盤の意識と“大阪起点”戦略
維新は大阪発祥の政党であり、大阪を中心とした地方自治・行政改革の旗手という位置づけが強い政党です。報道でも、「維新がいきなり与党に入ると地元大阪への説明が必要」という指摘がありました。
つまり、維新としても「全国展開を果たしたいが、地元での支持基盤を崩したくない」「与党入りするならば準備期間が必要」という慎重姿勢があったことが、連立協議を“即入閣”ではなく“閣外協力”という形でスタートさせた背景と考えられます。
公明党の離脱と維新への協力要請の背景
自民・公明という長年の“自公連立”が揺らぎ、今回維新がその枠組みに加わるという動きになったのには、公明党側からの離脱・離反が大きく関係しています。
✔ 公明党離脱の原因
- 報道によると、公明党は自民党・維新との連立入りを含めた政策協議において、「政策と理念の一致」が非常に重要だという立場を鮮明にしていました。公明党の斉藤代表は、「維新の皆さんは政治とカネの問題についても厳しい姿勢をとってこられた。連立ならその点もきちんと協議を」と発言しています。
- また、記事によれば、公明党側には「従来の自公連立の枠組みが限界に来ている」「政治資金・団体献金問題などで与党が国民からの信頼を失っており、新たなパートナー探索が必要ではないか」といった内部の声もあったと指摘されています。
- ゆえに、公明党は自民党との連立を「継続可能だが、無条件ではない」と位置づけ、維新との政策協議を視野に入れつつ「自らの理念・信条を譲れない」というスタンスを強めていたようです。
✔ 維新への協力要請の理由
- 自民党としては、公明党のみでは過半数を確保しづらい、あるいは今後の政策運営・選挙環境を考えると“将来パートナー”を多様化させておいた方が安全だという判断が出ています。例えば、離脱の可能性がある公明党に代わる「補強勢力」として維新が浮上していたという分析が出ています。
- 維新自身が「与党入り/協力」を排除しておらず、自民との政策接近も進めていたため、自民側から維新にアクセスしやすかった、という構図もあります。
- さらに、維新をパートナーに据えれば、「改革派」「地方派」「若手層支持層」というイメージを与え、自民党の“刷新”あるいは“リブランディング”にも資するという期待もあったと思われます。
✔ 公明‐維新の直接的な交渉からの行方
- 公明党の側で「維新とは協力できるかもしれない」という発言がある一方で、維新自身は野党時代、自民‐公明の枠組みを構成する連立に対して慎重・批判的な立場を取っていた歴史もありました。維新と公明では、政策・支持基盤・理念に一定の違いがあったため、協議がスムーズには進まなかった――という見方があります。
- 結局、公明党は“自公連立継続”を断言せず、どちらかというと“自公+維”という三党枠組みの可能性も探りながら、自党の立ち位置を模索してきた、と言えそうです。これが「公明離脱」の伏線になったとも考えられます。
野党側(立憲・国民・参政)との“連携”模索と不決着の様相
維新が自民と連立を組む方向に動いた一方で、野党側でも「自民・公明モデルに対抗する形で、自分たちの協力構図を作れないか」という動きがありました。ですが、結果としては“まとまり切らなかった”というのが現状です。
立憲民主党・国民民主党との関係
- 例えば、記事では次のように述べられています。公明党との交渉が難航する中、「国民民主党の玉木雄一郎代表を首相とするシナリオ」が野党内で浮上していたというものです。
- 立憲民主党・国民民主党・維新・公明という4党が結べば223議席を超えるという数の読みも出ていました。
- しかし、政策的な“温度差”・支持基盤の違い・過去の対立関係などが障壁となり、協議が本格化しておらず、維新も野党側との連携に積極的に踏み込んでいたわけではない、という状況がありました。たとえば、維新の馬場代表は「自民との連立を排除せず」という発言もしており、野党側との協力一辺倒というスタンスではなかったのです。
参政党の存在と“第三極”模索
- また、参政党の台頭も、政界構図を揺るがす“変数”となっていました。ある識者のコメントでは、与党・野党双方において「参政党の影響を軽視できない」とされています。
- 参政党が“既存政党への不満”を背景に支持を伸ばしている中、政党間では「野党共闘をどう構築するか」「第三極との関係をどう整理するか」という議論が起きていたものの、統一行動を取るには至っていません。
結局、何が壁になったか?
- 政策の優先順位/理念的連携:立憲・国民・維新では、教育、分配、社会保障、外交・安全保障において優先項目が異なっており、一枚岩になることが難しかった。
- 支持基盤・地域構造の相違:維新は大阪発の地方政党色が強く、立憲・国民は全国展開の中で都市部・中間層支援が強い。
- 過去の競合・対立関係:維新と立憲・民主系とは過去に選挙で競合したり、政策論争をしてきた歴史もあり、協調に対して警戒感があった。
- 数の読みとタイミング:自民・維新という枠組みが先に動いたことで、野党側は「その後追い」という形になり、主導権を握りきれなかった。
結果として、野党側の連携は「模索」の域を出ず、維新は既に自民側との協議に傾いていったというのが実際の動きです。
連立合意の「裏側」〜制度・駆け引き・生き残り戦略
ここでは“駆け引き要素”や“制度的観点”を少し掘ってみましょう。読んでいて「へぇ、こんな視点もあるのか」と思えるような豆知識も交えます。
閣外協力という“抜け道”
報道では、維新が連立に合意したものの、当面は「閣外協力(入閣せず、立法支援等で与党を支える)」というスタイルを採るという分析があります。
【豆知識】
“閣外協力”という言葉は、政党が政府(内閣)には閣僚を出さずに、政策協議・議会支援という形で協力するスタンスを意味します。
政権の責任を取りたくない場合や、与党と距離を保ちつつ影響力を持ちたい場合に使われることがあります。
維新の場合、「入閣すると地元説明/責任が重くなる」「人材をそろえる準備がまだ」という地元大阪事情もあり、敢えてこの道を選んだという解説があります。
政策協議の「カード化」
維新と自民の協議において、維新側が「大阪都構想」「定数削減」「税制・教育改革」などいくつかの旗を掲げ、自民側はそれを交渉材料として扱ってきました。報道では「維新が入閣を急がず“交渉カード”を確保した」というコメントも出ています。
このような「交渉カード化」は、政党が連立という枠組みに入る際、自らの影響力を最大化する戦略としてしばしば使われます。維新としては「今は閣外協力でも、実績を出して影響力を強め、将来入閣もありうる」といった準備段階という位置づけが窺えます。
地方基盤・大阪の意義
維新は大阪を拠点としてきた政党であり、「地方発、全国政党へ」の流れを重視してきました。ですから、中央政界(東京/霞が関)に深く入り込むことには慎重さもありました。前述の通り、専門家の指摘では「地元(大阪)への配慮」が維新の決断に影を落としていると分析されています。
この点で、維新が「まずは閣外協力」という形を選んだのは「地方基盤を崩さず、中央との協力関係を探索する」という戦略的選択とも読み解けます。
自民の“求心力弱化”と連立模索
自民党としては、長年の与党としての安定基盤が揺らぎつつあるという危機感がありました。たとえば、参院選での与党側の苦戦や、有権者の既存政党離れ、さらに第三極(参政党等)の台頭などが、既存の枠組みを変えざるをえない状況を作ったという指摘があります。
このため、自民としては「従来の連立パートナー+幅広い協力勢力」という構えを改め、維新のような改革志向・地方重視の政党を取り込むことで“新しい枠組み”を模索した、という背景があります。
選挙時期・制度改革の視点
“将来の解散・総選挙”を念頭に置いた勢力拡大・連携模索もあります。政権基盤が弱まる中で、次の衆参同日選・解散総選挙への備えとして、与党側・連立側双方が“数の安全装置”として維新を見ていた可能性があります。
また、維新が主張してきた「議員定数削減」「小さな政府」「地方分権」などの制度改革志向は、新しい与党枠組みにおいて“改革を求める層”の受け皿になりうるという評価もありました。
今後の焦点:実行・亀裂・維持可能性
連立合意に至ったとはいえ、今後がスムーズに行くとは限りません。いくつかの注目点があります。
実行力と“政策の擦り合わせ”
維新と自民の間で提示されている共通項もありますが、細部では相違点も多く残っています。特に「財政支出のあり方」「社会保障費の改革」「地方交付税の見直し」「教育政策」など、利害が激しく交錯する分野では、調整が不可避です。報道でも「改憲・安全保障・地方分権・議員定数削減」など維新が重視する項目が挙げられています。
連立合意書には「維新の議員が閣僚を出さない」「閣外協力」という形も想定されており、これは“条件付き”の協力という意味合いが強く、いずれ“入閣かどうか”という選択に議論が移るかもしれません。
維新にとってのリスクが与党寄りになり過ぎることで“野党”としての改革志向・無党派層からの支持を失う可能性が大。
特に、大阪を支える地元支持層から「政府に迎合しすぎている」という批判が出るかもしれません。
自民にとってのリスクは、維新を取り込むことで政策の軸がぶれる、あるいは維新色(地方分権・議員定数削減)を通すことで既存支持層/与党派閥から反発を受ける可能性が大。
そして、維新との協力が長続きしないという見方もあり、「連立を組んだらいずれ捨てられる(維新前原誠司・談)」という発言も過去に出ています。
維持可能性・将来の展開
今回の合意は、まず「首相指名選挙での支持」「議会運営での協力」というスタイルを踏み出し、「入閣を含む連立政権」という次段階へつなげる流れと見られています。たとえば、報道では今回の合意が「100代目の内閣総理大臣に女性・高市早苗氏が就任する道を開いた」とされています。
将来的に、維新が閣僚ポストを得るか/得ないか、また協力関係を維持できるかという点が焦点になります。維新自身が“カードを温存”しておきたいというスタンスを示していた点が、今後の鍵となるでしょう。
また、野党側もこの構図変化を受けて再編を模索するでしょう。特に、立憲・国民・参政といった政党がどう動くか、維新を取り込めば“野党連合”としての可能性もありますが、現時点では“決裂”に近い形となっています(前述の通り)。
まとめ
要点を整理すると、以下のようになります。
- 自民党が従来の“自公連立”だけでは将来の議席・政策運営の不安を抱えており、維新をパートナーとして取り込みたいという構えがあった。
- 維新は、政策実現・地方基盤維持・全国展開という観点から、自民との協力を視野に入れていた。
- 公明党は、自民との理念・政策のズレを感じつつ、自らの立ち位置を模索しており、結果的に“離脱/枠組み再構築”の方向が強まった。
- 野党側も協調を模索していたが、維新との政策的・戦略的ズレ、支持基盤の違いなどから、連携をまとめ切れなかった。
- 連立合意の裏側には、「閣外協力」という維新の戦略、「交渉カード化」という維新の駆け引き、「地方基盤を大切にする」という維新の慎重姿勢、「新旧パートナー关系の崩壊」という自民・公明の構図変化があった。
- 今後の焦点は、実行政策の整合性、維新・自民間の亀裂の有無、維新が入閣を選ぶかどうか、そして野党再編の動きです。
豆知識コーナー
- 「閣外協力」という言葉:政党が政府に参加せず、閣僚を出さず、政策協議や議会支援という形で政府を支えるスタイル。責任を共有しづらいが、影響力を持つことができる。
- 維新の綱領における三つの「自立」:個人自立、地方自立、国家自立。地方自治・道州制を強く打ち出している。
- 支持基盤の構図:維新は大阪を出自とし“地方改革”をキャッチフレーズにしてきたため、中央政界に入りすぎることへの慎重さがあるという指摘あり。
 ヒロ
ヒロここまで、いかがですか?
真相がおおまか分かったのではないでしょうか?
こう見てくると、維新も公明以上にしたたかです。
万年野党も嫌気がさしてきていたのかもしれないですね。与党でないと我が党がいかにいい政策を立案しても、すべて廃案となるわけですから。



そうですね。
副首都構想を目論む維新にとって、今回のチャンスは絶好の与党入りのチャンスだとにらんだのかもしれないですね。
数の論理か。
国会議員削減法案を提出してもらって、仕事をしない余計な国会議員はやめてもらったほうがいいと思います。
歳費はすべて国民の税金なのですから。
もっと分かりやすく・・・自民党×維新の“新しい連立政権”誕生!
~なぜ今? その裏にある理由をここから、超わかりやすく解説します~
🌸 はじめに:日本の政治が動いた日
2025年10月20日。日本の政治に大きなニュースが飛び込みました。
「自民党と日本維新の会が、ついに連立政権を組むことで合意」したのです。
これまで30年以上にわたり、自民党は公明党と手を組んで政権を維持してきました。
それが、ついに「自公」から「自維」へと変わる――。
まさに“平成政治の終わり、令和政治の始まり”とも言える大転換です。
でも、「なんで?」と思う人も多いでしょう。
自民と維新は、もともと意見が違う部分も多かったはず。
なのに、どうして一緒にやることになったのでしょうか?
🧩 背景:自民党の“数の不足”と“公明党の不満”
政治の世界では、「数(議席)」が命です。
国会で法律を通すには、多くの議員が“賛成”してくれなければなりません。
ところが最近の選挙で、自民党と公明党を合わせてもギリギリ過半数、という状況が続いていました。
そこに公明党の不満が噴き出しました。
「自民党は私たち(公明)の意見を軽く扱っていない?」
「政策で譲れない部分が多すぎる」
そんな声が増え、公明党は距離を置き始めます。
一方、自民党には焦りが出ます。
「公明が離れるなら、新しいパートナーを探さないと政権がもたない!」
そこで白羽の矢が立ったのが――
改革志向で若い支持層を持つ、日本維新の会 だったのです。
💡 維新の会が“連立参加”を決めた理由
では、維新の会はなぜ連立に乗ったのでしょう?
実はこれにも、いくつかの理由がありました。
① 政策の方向性が似てきた
維新は、「無駄をなくす」「税金の使い方を変える」「地方を元気にする」など、
“改革”を旗印にしてきた政党です。
一方、自民党も近年は「行政改革」や「憲法改正」「安全保障強化」に力を入れています。
つまり、“国を強くする方向”では一致していたのです。
特に「防衛力強化」「地方の自立」「議員定数削減」など、
維新の主張が自民とかぶる部分が多くなってきました。
② 維新も「実績」が欲しかった
これまで維新は「改革の旗」を掲げてきましたが、野党ではできることが限られます。
「言うだけ」ではなく「やる政治」に進むためには、
政権の中に入ることが最も近道なのです。
つまり維新は、
「自分たちの政策を実現するために、あえて与党側に回ろう」
という決断をしたのです。
ただし、いきなり「大臣ポストをもらう」わけではなく、
まずは「閣外協力(=内閣に入らず協力する)」という形で様子を見るスタイルです。
③ タイミングが絶妙だった
政治では「タイミング」が命です。
ちょうど自民と公明の関係が悪化していた時期に、
維新は「連携を排除しない」と発言していました。
これは、いわば“準備万端のタイミング”。
公明の穴を埋める形で、維新がすっと入った――という構図です。
④ 地方政党から“全国政党”へ
維新の出発点は大阪です。
「大阪都構想」など、地方行政の改革を進めてきた政党ですが、
最近では全国に支持を広げようとしています。
そのためにも、国政の中心で影響力を持ちたい。
今回の連立は、まさに維新にとっての“全国進出の第一歩”だったわけです。
⚖️ 公明党の離脱:長年の連立にヒビ
長年連立を続けてきた公明党が、どうして離れたのか。
主な理由は3つあります。
- 政策のズレ:
公明党は「福祉」「教育」「生活支援」を重視しますが、
自民は「経済」「防衛」「財政再建」を優先します。
この違いが年々大きくなりました。 - 選挙での摩擦:
選挙区調整で、自民が強引に候補を立てたことが公明を刺激。 - 信頼関係の亀裂:
「昔のような協力関係ではなくなってきた」と言われるほど。
こうした中で、自民は「新しいパートナー」を探す決断を下したのです。
🏛 野党たちの動き:協力できず“不発”に
立憲民主党・国民民主党・参政党なども、「自民・維新に対抗しよう」と動きました。
でも、政策の方向性や支持層の違いから、まとまりませんでした。
- 立憲は「社会保障や人権を守る」立場
- 維新は「改革・小さな政府」志向
- 国民民主は「中道バランス型」
それぞれの思惑が違い、話が進まなかったのです。
結果、維新は「野党連携」よりも「自民との協力」を選んだという流れです。
🎯 今後どうなる?
今回の「自維連立」は、まだ始まったばかり。
維新は閣僚を出していませんが、今後の政策次第で入閣の可能性もあります。
主な注目ポイントは次の通りです👇
| 注目点 | 内容 |
|---|---|
| 💬 政策の一致点 | 憲法改正・防衛力強化・地方分権 |
| ⚠️ 意見が割れそうな点 | 税金の使い方・教育支援の範囲 |
| 🧭 維新の立ち位置 | 「与党の中の改革派」になるか「第二与党」に留まるか |
| 🗳 選挙への影響 | 若者や無党派層の動きがどう変わるか |
🌸 まとめ:令和の政治は“流動化”の時代へ
今回の「自民×維新」連立は、
単なる政党の組み合わせ変更ではありません。
- 自民党:長期政権の“若返り”を狙う
- 維新:改革勢力として“全国化”を狙う
- 公明党:独自路線への再出発
それぞれの思惑が重なり合い、
日本の政治は「固定された連立」から「動く連立」へと変わろうとしています。
これから数年、政界では「再編」や「新党誕生」が続くかもしれません。
政治は動く生き物――今回の連立は、その“序章”にすぎないのです。
🪶 ヒロの一言メモ
政治のニュースって難しく聞こえるけど、
要は「チームをどう組むか」の話。
自民がチームのリーダーで、維新が新しい副キャプテンになった。
これからの日本がどう変わるか、私たちも“観客”ではなく“有権者”として見守っていきたいですね。
おわりに・・・《令和日本、初の女性総理誕生へのカウントダウン》
日本政治における大きな転換点が、今まさに訪れています。長らく続いた与党の枠組み、つまり 自由民主党(自民) + 公明党(公明)による“自公連立政権”が変わろうとしています。そしてその変化の中心には、日本維新の会(維新)が自民と手を結び、さらに女性初の首相候補として高市早苗氏の登場が待たれている――という構図があります。
まず、なぜ「自維連立」に至ったのか。整理すると、ひとつには「議席・数の論理」が大きく働いています。政権を安定して運営するためには、与党に十分な議席数が必要ですが、公明との従来の枠組みだけではその安全圏が揺らぎつつありました。ここに維新という改革志向・地方基盤を持つ政党を組み入れることで、自民側は新たな“数の補強”とイメージ刷新を同時に狙ったのです。
維新側も、単に野党で改革の旗を振るだけでは限界を感じており、実際に政策を動かす実績を得るためには与党側との協力が現実的だと判断したようです。彼らが自ら「与党としての協力も排除しない」と明言していたことも、今回の動きの伏線でした。
次に、公明党の離脱と維新への協力要請という構図です。公明党は、長年の自民との連立において「理念・政策のズレ」を深めており、特に生活支援・福祉・教育といった分野での自民とのすれ違いが顕著になっていました。その結果、公明は「無条件の自公継続」ではなくなり、自民は次のパートナーを探さざるを得なくなったのです。そして維新がそこへ入り込んだ。
さらに、野党側(立憲民主党・国民民主党・参政党)も協力構想を模索していましたが、政策・理念・支持基盤のバラつきがあり、結局まとまり切りませんでした。維新としても「野党とともに」というよりは「改革の実現と影響力拡大」を優先し、自民との協議へ傾いたことが目立ちます。
そして迎えるのが、高市早苗氏の首相誕生の可能性。
自民と維新が連立合意に至ったことで、次期臨時国会での首相指名選挙において「高市氏を選出する」という見通しが大きく強まりました。
日本の歴史上、女性が内閣総理大臣に就任した例はなく、その意味でも象徴的な瞬間といえます。
このタイミングでの高市氏の登場には、政策面でも注目すべき意味があります。行政改革、地方分権、憲法改正、安全保障強化――これら維新と自民双方が掲げてきたテーマが重なっており、高市氏を軸とする政権は「改革・変化」をアピールしやすい体制といえそうです。
ただし、連立の“始まり”である以上、課題も多々あります。維新側が閣外協力という形を選んだ背景には、「すぐに入閣せず影響力を温存したい」という戦略があります。逆に自民側は、維新を取り込むことで従来支持層の反発を招く可能性があります。政策の擦り合わせ、与党内の亀裂、維新と自民の立場のズレ……これら全てが、今後の政権運営に影を落としかねません。
とはいえ、この転換点を「機会」と捉える視野もあります。日本政治が“固定された枠組み”から“流動する枠組み”へと移りつつある今、与党・野党を超えた協力・再編が鮮やかに動き出しています。そしてその象徴的な瞬間が、まさに高市早苗氏が初の女性首相として誕生するかもしれない、という点です。
ヒロの声



今、令和の政治の大転換期にきているのかもしれません。
今までの自民一党の政治に国民は嫌気がさしているのがよく分かります。この物価高で国民は怒っています。
だから、高市さんには、なんとかこの苦しい状況を打開してほしい。その思いで、国民は間接的に高市さんを推しているのです。
そこが理解できていないと、石破さんの二の舞になります。
高市さんならなにか変えてくれそう。
そんな国民の心の声をしっかりと高市さん、読み取ってください!!



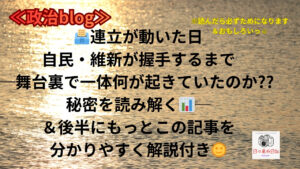

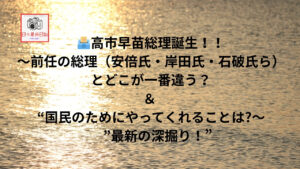
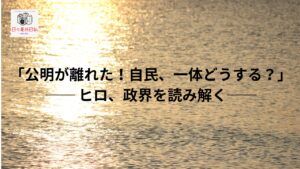
コメント欄