はじめに:10年後を見据えた“長期投資”という考え方
 ヒロ
ヒロこんにちは、ヒロです。
株式市場では、目先の上げ下げに一喜一憂するニュースが多いですが、実際に「資産を大きく育てる投資」を考えるなら、
焦点を当てるべきは“10年後にどうなっているか”です。
たとえば、10年前の日本株を振り返ってみると、
当時はまだAIブームも半導体バブルも到来しておらず、
クラウドSaaSなども一部のIT企業の言葉でしかありませんでした。
しかし、そこから時代は激変。
生成AI、IoT、DX、そして在宅ワークの常態化によって、
「ITインフラを支える企業」が急成長した10年でもありました。
そして今。
「次の10年の主役」を探すなら、
再び注目すべきは“1000円台で買える中堅IT株”です。
今回は、特に話題性と将来性の両方を兼ね備えた
2つの銘柄――
📈 ラクス(3923)
💻 サイバーエージェント(4751)
この2社を比較しながら、
どちらが“10年後に真の勝者”になっているかを、
プロ投資家の視点で掘り下げていきます。
第1章:なぜ今「1000円台のIT株」が注目されるのか
まず、なぜあえて「1000円台」という価格帯に注目するのか。
それは、中堅成長株の黄金ゾーンだからです。
- 既に上場し、業績も安定している
- とはいえ、まだ大型株ほど過剰評価されていない
- 将来の拡大余地が残されている
つまり、企業としては「実績も芽もあるが、まだ上値余地がある」――
そんなステージが1000円台付近なのです。
また、PER(株価収益率)やPBR(株価純資産倍率)が割高でも、
今後10年のEPS(1株当たり利益)成長率が高ければ、
“今の割高”は10年後には“割安”になります。
たとえば、ラクスのように年率20%成長を10年間続ければ、
売上は約6倍、利益は約10倍近くに拡大する可能性もあります。
(単利ではなく複利成長の力は絶大です)
この“成長倍率の妙”こそが、
1000円台の成長株を狙う醍醐味です。
📊 コラム:PERとはなに?〜初心者でもスッと分かる株の“ものさし”〜
🪙 PER(ピー・イー・アール)=「株の割安・割高を測る物差し」
株式の世界でよく出てくる「PER」という言葉。
これは Price Earnings Ratio(株価収益率) の略で、
その会社の株が、今の利益に対してどれくらい高く買われているか を示す数字です。
かんたんに言うと──
💬「会社の1年分の利益の何倍の値段で、その株が取引されているか」
ということです。
🧮 計算式はとてもシンプル
PER=株価÷1株あたりの利益(EPS)
たとえば、
ある会社の株価が1,000円で、1株あたりの利益が100円だったとします。
→ その会社のPERは 1,000÷100=10倍
となります。
つまり、「利益の10年分の値段で、その株を買っている」というイメージです。
💡 PERが意味する「割高」「割安」
| PERの目安 | 見られ方 | 投資家のイメージ |
|---|---|---|
| 10倍前後 | 適正または割安 | 利益に対して妥当な価格 |
| 20〜30倍 | 成長期待株 | 今後の利益増を期待して高く買われている |
| 50倍以上 | 超成長株 or 過熱気味 | 将来の利益に大きく賭けている状態 |
| 5倍以下 | 割安 or 業績悪化懸念 | 安いけどリスクもあるケース |
たとえば、ラクスのような「成長中のSaaS企業」は、
将来の利益拡大が見込まれているため PERが30〜40倍でも許容範囲 とされます。
一方、成熟した企業(例えば銀行・鉄鋼・電力など)は、
成長が緩やかなので PER10倍前後 が目安です。
📈 PERは「高い=悪い」ではない!
初心者がよく誤解するのが、
「PERが高い=割高で買ってはいけない」という考え方。
実はこれは半分正解、半分まちがいです。
たとえば、今はPER40倍の企業でも、
10年後に利益が10倍になれば、実質的にはPER4倍相当 になります。
つまり、「今は高くても、将来の成長で帳尻が合う」 ということです。
逆にPERが低くても、
利益が減り続ける企業は“安いようで高い”場合もあります。
🏁 まとめ:PERを“温度計”として使おう
PERはあくまで「株価の温度計」のようなもの。
- 高すぎれば、熱がこもっている(=人気先行)
- 低すぎれば、冷え切っている(=期待されていない)
つまり、PER単体ではなく、
「その企業の成長率」や「業界平均」とセットで見ることが大事です。
💬 例で覚えよう!
| 企業 | 株価 | 1株利益(EPS) | PER | コメント |
|---|---|---|---|---|
| A社(成長中) | 1,000円 | 50円 | 20倍 | 成長株。将来性を織り込み済み。 |
| B社(安定型) | 1,000円 | 100円 | 10倍 | 妥当水準。配当狙いもあり。 |
| C社(低迷中) | 1,000円 | 20円 | 50倍 | 割高。人気先行の可能性あり。 |
🌱 ヒロから一言
PERは「株を買うタイミング」を考えるうえで、
とても役立つ“入口の指標”です。
ただし、それだけで決めてしまうのは危険。
企業の成長性・利益率・将来の見通しと組み合わせて見ると、
より確かな判断ができます。
📊 PERは「今」の温度。未来を見るには「成長率」とセットで!
第2章:ラクス(3923)―中小企業クラウドSaaSの雄
ラクスは、中小企業の業務効率化を支援するクラウドSaaS企業です。
代表的なサービスは以下の通り:
| サービス名 | 内容 |
|---|---|
| 楽楽精算 | 経費精算のクラウド管理 |
| 楽楽明細 | 請求書や納品書の電子発行 |
| 楽楽勤怠 | 勤怠管理のクラウド化 |
| 楽楽販売 | 営業・受注業務をクラウド管理 |
これらのサービスは、いずれも**定期課金(SaaSモデル)**で運営され、
ストック収益が積み上がっていくビジネスモデルです。
✅ 成長スピードが圧倒的
2025年3月期の決算では、
- 売上高:489億円(前年+27%)
- 営業利益:101億円(前年+83%)
と、驚異的な伸びを見せています。
さらに、2026年3月期の会社予想も
- 売上:594億円(+21%)
- 営業利益:149億円(+47%)
という高成長を継続。
しかも、営業利益率は26%前後に上昇しており、
利益体質の改善が進んでいます。
✅ 強いストック構造
ラクスの最大の強みは「MRR(月次課金収益)」です。
クラウド事業の売上比率はすでに80%超。
契約を積み上げれば安定収益となり、
10年後も一定の顧客が継続している可能性が高い。
さらに日本では、まだ中小企業のデジタル化率が低く、
市場の成長余地が大きい。
第3章:サイバーエージェント(4751)―エンタメ×AIの巨人
一方のサイバーエージェントは、
言わずと知れたデジタル広告・ゲーム・メディアの三本柱を持つ大企業。
| 事業区分 | 内容 |
|---|---|
| インターネット広告事業 | 国内No.1のデジタル広告代理店 |
| メディア事業 | ABEMA・Amebaブログなど |
| ゲーム事業 | ウマ娘、プリコネなどの大ヒット作 |
✅ 収益力の復活
2025年9月期は、営業利益660億円(前年+57%)見通し。
特に「ゲーム事業」と「広告AI最適化」が牽引。
生成AIを活用した広告配信技術により、
効率的な広告出稿・運用が可能になりつつあり、
AI関連銘柄としても注目を浴びています。
✅ メディア拡大の可能性
ABEMAは依然として赤字ですが、
スポーツ中継・ドラマ配信の拡充によって、
「黒字転換の兆し」が出ています。
10年後を見据えると、
サブスク+広告のハイブリッド収益モデルへの進化が期待されます。
第4章:両者の“10年後シナリオ”を比較
| 観点 | ラクス | サイバーエージェント |
|---|---|---|
| 主力領域 | 中小企業向けクラウドSaaS | 広告・メディア・ゲーム |
| 成長率 | 売上+20〜25%/年 | 利益変動型(新作・広告次第) |
| 営業利益率 | 約26% | 約12〜14%(変動あり) |
| リスク | SaaS競争、海外展開の壁 | ゲームヒット依存、景気変動 |
| 安定性 | 高(ストック収益) | 中(事業ポートフォリオ広) |
| 10年後の期待 | 国内SaaSの代表格 | AI×広告で再成長も波あり |
💡 プロ投資家の見立て
私は長期的にはラクスに軍配を上げます。
理由は以下の3点です:
- 成長ストーリーが明確である(SaaS×中小企業×DX)
- 利益率が高く、景気に左右されにくい
- 株価がまだ“割高すぎない”
一方、サイバーエージェントはエンタメ業界の巨人。
「AI広告」「ABEMA黒字化」「新作ゲーム」の3本が噛み合えば、
短期的な爆発力はラクスを上回る可能性があります。
つまり、
- 長期安定・積み上げ型の投資 → ラクス
- 波乗り・イベント型の投資 → サイバーエージェント
という棲み分けが適しています。
第5章:10年後の株価予想シミュレーション
これはあくまで筆者の仮定シナリオですが、
以下の前提でシミュレーションしてみましょう。
ラクス
- 売上成長率:+20%/年
- 営業利益率:26%
- PER:35倍維持
→ 10年後の利益は現在の約8〜10倍規模。
→ 理論株価は今の約6〜8倍(6000〜8000円)も視野。
サイバーエージェント
- 利益成長率:+8%/年
- PER:25倍(景気・業績で変動)
→ 10年後の利益は約2倍程度。
→ 理論株価は2000〜2500円程度に上昇余地。
もちろん、AI革命やメタバース次第では
サイバーエージェントの方が一気に化ける可能性もあります。
しかし、“確度の高い成長”という意味ではラクスが一歩上です。
第6章:投資スタイル別おすすめ
| 投資スタイル | 向いている銘柄 | 理由 |
|---|---|---|
| コツコツ積立型 | ラクス | 安定したSaaS収益、成長予測が立てやすい |
| イベント狙い型 | サイバーエージェント | 新作ヒット・AI事業・広告好況で短期上昇も |
| 配当重視型 | どちらも非該当 | 成長株のため配当は薄い |
| 10年長期保有 | ラクス | “長期の複利成長”を享受できる |
第7章:ヒロのまとめと所感
「10年後に勝つ株」というテーマは、
結局のところ、“今の成長ストーリーがどれだけ持続するか”に尽きます。
ラクスは、堅実なビジネスモデルと高い利益率で、
10年後も着実に利益を積み上げている姿が想像できます。
一方サイバーエージェントは、
創造と挑戦の企業文化を持ち、AI・広告・エンタメの分野で
“何かを仕掛けてくる”面白さがあります。
だからこそ、
✔️ 手堅く資産を育てたい人は「ラクス」
✔️ ドラマのようなストーリーに賭けたい人は「サイバーエージェント」
この2社を軸に、ポートフォリオを分散するのも一つの戦略です。
結びに:次の10年、投資家が見るべき視点
10年後の世界では、
AI・自動化・クラウド・エンタメすべてが今より深く結びついているでしょう。
今の1000円台の株が、
その中心に立つ可能性は十分にあります。
ヒロとしては、
「小さな種を10年かけて大樹に育てる」――
そんな投資を、読者の皆さんと一緒に楽しみたいと思います🌱
💬 まとめ(短く要約)
- ラクス:SaaS・中小企業DXの成長エンジン。利益率◎・安定感◎
- サイバーエージェント:AI×広告×ゲームの革新企業。波あり・伸びしろ大
- 長期投資ならラクス、波乗り投資ならサイバーエージェント!
💡 あなたなら、どちらを選びますか?
コメント欄やSNSでぜひ教えてください👇
#株式投資 #ラクス #サイバーエージェント #長期投資 #IT企業株 #AI投資 #10年後の成長株
📘 コラム:PBRとはなに?〜会社の“資産価値”と株価の関係を知ろう〜
株のニュースや証券サイトでよく見る「PBR(ピー・ビー・アール)」という言葉。
「PER」とセットで出てくることが多いですが、
こちらも株の“割高・割安”をはかるための指標のひとつです。
でも、PERが「会社の利益」に注目するのに対して、
PBRは「会社が持っている資産」に注目している点が大きな違いです。
💡 PBRとは?
PBRとは Price Book-value Ratio(株価純資産倍率) の略です。
かんたんに言えば――
💬「その会社の“資産”に対して、今の株価が何倍で取引されているか」
を表す数字です。
もう少し具体的に言うと、
会社が持っている資産(現金・土地・工場・設備・知的財産など)から
借金を引いた“純資産”をもとに計算します。
🧮 計算のイメージ
PBRの計算式はとてもシンプルです。 PBR=株価÷1株あたりの純資産
たとえば、
ある会社の1株あたりの純資産が1,000円、
株価も1,000円だったとします。
この場合、
1,000 ÷ 1,000 = PBR 1倍 になります。
つまり「その会社が持っている資産と、株価がちょうど同じ価値で取引されている」という状態です。
🔍 PBRの見方(直感で覚えよう)
PBRの数字を見るときは、
ざっくり次のように考えるとわかりやすいです。
- PBRが1倍より低い → 株価が“資産価値より安い”=割安株
- PBRが1倍より高い → 株価が“資産価値より高い”=期待が高い株
たとえば、PBRが0.8倍の会社は、
「1,000円分の資産があるのに、株価が800円」という状態。
つまり、会社を解散して資産をすべて売ったら、
今の株価よりも多くのお金が戻ってくるかもしれない――そんな“お買い得”な状態を示します。
一方で、PBRが3倍、5倍と高い会社は、
資産の価値以上に将来の成長性が期待されている状態です。
💬 PBRが低ければ“お得”なの?
ここがポイントです。
PBRが低いからといって、必ずしも「買い得」とは限りません。
なぜなら、会社の資産があっても、
それをうまく活かせずに利益を出せていないケースもあるからです。
たとえば、老朽化した工場や使われていない土地をたくさん持っているだけでは、
企業価値はなかなか上がりません。
逆に、PBRが高い企業でも、
知的財産やブランド、テクノロジーなど「見えない資産」が強ければ、
高い評価を受けて当然です。
🏦 では、どんなときに使うの?
PBRは、「その会社がどれくらい効率的に資産を使って利益を生み出しているか」
を見るときに役立ちます。
たとえば、PBRが1倍を下回っている会社の中でも、
最近業績が回復してきている企業は“再評価される可能性”があります。
つまり、PBRは「市場がその会社をどれだけ評価しているか」を映す鏡なんです。
🧭 PERとの違いをざっくり整理
PERは「利益」と株価の関係。
PBRは「資産」と株価の関係。
どちらも“割高・割安”を判断する指標ですが、
PERが“稼ぐ力”、PBRは“持っている力”を見ています。
💬 PER=会社の「儲ける力」
💬 PBR=会社の「持っている価値」
この2つをあわせて見ることで、
「この会社はどんなタイプの成長をしているのか」が見えてくるのです。
🌱 ヒロから一言
PBRは、株式投資の中でも「会社の中身を知る」ための大切な指標です。
特に長期投資を考えるとき、
「この会社は資産をちゃんと生かしているのか?」を確認するのに役立ちます。
ただし、PBRの数字だけで判断してはいけません。
利益を出せる企業(=PER)と、
資産をうまく使える企業(=PBR)は、似ているようでまったく違います。
💬 PBRは、企業の“基礎体力”を映す鏡。
数字よりも、その資産をどう活かすかを見るのが投資家の目線です。
🔔 最後に:PERとPBRのちがいをやさしくまとめよう
ここまで読んでみて、「PERとPBR、似ているようで何が違うの?」と思った方もいるかもしれません。
実はこの2つ、どちらも“株価が高いのか安いのか”を判断するための道具ですが、
見ている“角度”がまったく違うのです。
💬 たとえるなら──
PERは「その会社がどれだけ儲ける力を持っているか」を示す“収益のものさし”。
PBRは「その会社がどれだけ資産を持っているか」を示す“財産のものさし”。
つまり、
- PERは「会社の稼ぐ力」を見る指標
- PBRは「会社の持っている価値」を見る指標
という違いがあります。
💡 もう少し直感的に言うと…
PERは「この会社は今、どのくらい利益を出している?これからどれだけ伸びそう?」を見る数字。
PBRは「この会社が持っている資産に対して、株価は高い?安い?」を見る数字。
PERが高い会社は、今の利益に対して株価が高い、つまり「将来の成長を期待されている企業」。
PBRが高い会社は、資産に対して株価が高い、つまり「資産を活かして大きく伸びそうな企業」。
反対にPERやPBRが低い場合は、
「いまは注目されていないけれど、復活すれば化ける可能性がある株」という見方もできます。
🪴 ヒロからのまとめ
PERとPBRは、どちらか一方だけで判断するものではありません。
この2つを組み合わせて見ることで、株の“性格”が見えてくるのです。
- PERが高くPBRも高い → 成長期待が大きい「人気株」
- PERが低くPBRも低い → 注目されていない「再評価待ち株」
- PERが低くPBRが高い → 利益は一時的に減っているが、資産価値が高い企業
- PERが高くPBRが低い → 将来性はあるが、まだ資産が小さい成長初期企業
💬 PER=稼ぐ力、PBR=持っている力。
どちらも“企業の鏡”であり、見る角度を変えると違う表情が見えてきます。
株式投資を続けていくうちに、
この2つの指標は自然と感覚的に読めるようになります。
だから今は、完璧に覚えようとしなくても大丈夫。
まずは「PER=利益」「PBR=資産」というイメージを頭に入れておくだけで、
ニュースの見え方がぐっと変わりますよ。
🌱 数字の裏には、会社の“物語”がある。
その物語を読み解く鍵こそ、PERとPBRなのです。

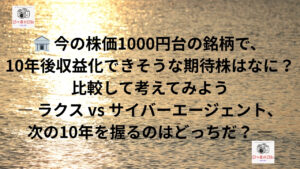
コメント欄