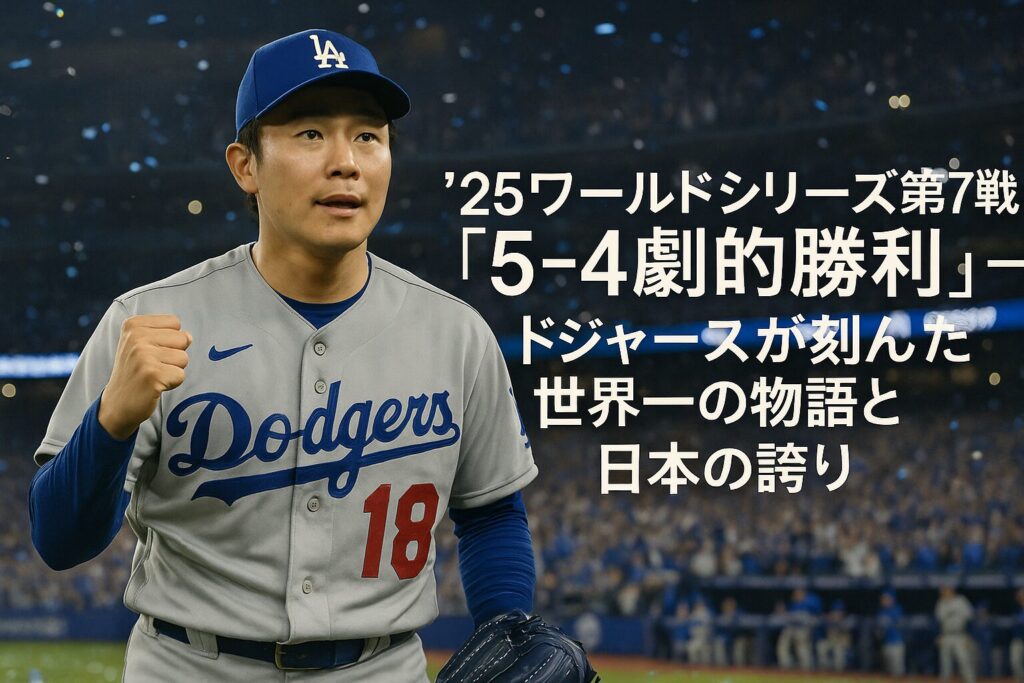
はじめに


朝8時50分、NHK BSのリモコンに指を伸ばした瞬間から、私の心拍数はずっと上がりっぱなしでした。画面の隅に映る“WORLD SERIES GAME 7”の文字、その下で揺れる青と白のウェーブ、実況の第一声――その全部が、今日がただの試合ではないことを告げていました。相手はブルージェイズ。青の軍団は序盤から集中力のスイッチが入りっぱなしで、外野席からの大合唱と手拍子がテレビ越しにも腹の底に響きます。球場を覆うカナダ国旗の赤と白、そして無数の“BLUE”のシャツ。あの圧巻の応援こそ、彼らが北の王者たらんとする誇りの証明だと感じました。

この第7戦は、まさにジェットコースター。点が入るたびに空気が変わり、わずかなミスで流れがひっくり返る。スコアボードの数字が移り変わるたび、私の膝も勝手に上下してしまいます。投手が一球外せばベンチの表情がこわばり、守備の一歩が早ければスタンドが爆発する。両軍の気合いの入れ方が尋常ではなく、序盤から“今日は誰も引かない”という覚悟が剥き出しでした。中盤には死球が重なり、ベンチ総出で一触即発。拳は交わらずとも、視線は完全に本気のそれ。審判が素早く両軍をなだめ、監督とコーチが体を張って選手を押し戻す様子に、第7戦の張り詰めた空気とプロフェッショナリズムを見ました。

それでも試合は続きます。青と白の声量がぶつかる中で、攻守の入れ替わりに合わせてドラマが連鎖していく。追いつかれ、また突き放し、そしてまた追いつかれて――テレビの前の私は、コーヒーを飲むタイミングさえ見失っていました。気づけば時間は正午を回り、解説の声も少し枯れている。それでも両軍の視線は鋭いままで、一本のヒット、一つの進塁打、一回の配球ミスで世界の天秤が傾くのだと、誰もが理解している表情でした。

終盤、スタンドの音圧はさらに増し、私は思わず画面に向かって“頼む、ここで決めてくれ”と呟いていました。結果はご存じのとおり、ドジャースが劇的な形で逆転に成功し、長い長い攻防の末に世界一連覇。テレビの時計は13時台後半、まさに14時前。私は両手を握りしめたまま数秒固まり、次の瞬間に立ち上がって叫んでいました。ブルージェイズは最後の最後まで強かった。だからこそ、この勝利は重く、そして美しかったのです。

加えて、今日は“テレビで観る野球”の幸福も噛み締めました。実況と解説の温度差、リプレーで映る指先の角度、俯瞰カメラが描く守備位置の妙。現地の熱を浴びる臨場感とは違うけれど、情報の網で試合を立体的に掴める。私はソファの上で、何度も画面に身を乗り出し、何度も深く背もたれに沈み込みました。これほど長い時間を“あっという間”だと感じた日は、そう多くありません。
💥 試合の概要
- 開始:朝8時50分
- 終了:13時50分ごろ(約6時間)
- スコア:5-4(延長11回)でドジャース勝利!
- MVP:山本由伸(ゼロ日登板・無失点リリーフ)
点が入るたびに会場が揺れ、
ブルージェイズの応援は“地鳴り級”。
テレビ越しでも心が震えました。
中盤には死球が続き、乱闘寸前の緊張感も。
それでも両チームが冷静さを失わず、最後までフェアに戦い抜いたのは本当に見事。
そして、延長11回のウィル・スミスの決勝ホームラン!
試合が決まった瞬間、私はテレビの前で立ち上がって叫びました。
第1章 “青”と“白”がぶつかった90フィートの戦場
この試合を支配していたのは、数字では測れない“空気の移動”でした。攻撃に入る前の円陣、投手がマウンドを踏む一歩、捕手がサインを出す指のわずかな間――そのすべてが連鎖して、スタンドの波とベンチの鼓動を同時に揺らします。ブルージェイズの応援は本当にすさまじく、攻撃のたびに巨大な壁のような音の塊がフィールドに押し寄せます。ドジャースの選手はそれを真正面から受け止め、淡々と自分の準備に戻る。第7戦にふさわしい精神力の殴り合いでした。

点の入り方も容赦がありません。先頭打者の出塁が、その後の全てを決めます。送るのか、強攻か、相手外野の肩をどう見るのか。三塁コーチの腕が大きく回れば、投内連携のスイッチが一斉に入る。たった一つのベースを奪うために、九人が同時に最適解を計算するあの感じ――それこそが“第7戦の野球”。小さなファウル一つにベンチが沸き、外野フライ一つにスタンドが息を呑む。私は画面に映るナインの所作に目を凝らし、何度も深呼吸を繰り返していました。
さらに、守備の一歩目がこれほど価値を持つ試合も珍しいと感じました。外野の背走、内野の前進守備、バントシフトの寄り方――どれもが“アウト一つの尊さ”を突きつけます。サードが前に出るたび心臓が跳ね、ショートの逆シングルに息を呑む。テレビ越しでも分かるほど各ポジションの初動が速く、双方のスカウティングと準備の質がにじみ出ていました。たとえ凡退でも、打者が次打席のために情報を持ち帰る姿勢に、王者と挑戦者の誇りを見ました。
【第7戦の“細部の強さ”チェックリスト】
・先頭打者への初球の入り方(見せ球か、ゾーン勝負か)
・二死からの四球を出さないこと
・外野の返球ルートと中継プレーの確認
・バントシフトの徹底と、フェイクバントへの備え
・内野ゴロでの一塁カバーと、送球の高さ
――どれもが当たり前のようでいて、第7戦では一つ漏れただけで命取りになる要件でした。
⚾ 両軍の気迫がぶつかった序盤戦
序盤から試合はハイテンション。
- ブルージェイズが先制!ゲレーロJr.が力強い打球を放つ
- すぐさまドジャースが反撃!ムーキー・ベッツの出塁→フリーマンのタイムリーで同点
- その後も点の取り合いが続き、球場のボルテージは最高潮に
🎯 ポイント
- 1回表:ジェイズ先制
- 1回裏:ドジャース同点
- 3〜6回:お互い一歩も引かずリードの奪い合い
中盤の死球連発では、両軍ベンチが総出に!
審判の冷静な対応で乱闘は回避されましたが、球場の空気は一瞬ピリッと張り詰めました。
第2章 乱闘寸前――死球が連鎖した数分間の真実

中盤、内角への厳しいボールが続き、死球が重なります。次の瞬間、ベンチから選手が雪崩のように飛び出し、両軍の輪がダイヤモンド上で膨らむ。ヘルメット越しに睨み合う目、止めに入るコーチの背中、主審の強いジェスチャー。あの数分は、時間の進み方が違っていました。ここで試合が壊れてしまえば、すべての努力が水泡に帰す。だからこそ、監督とコーチは声を枯らして理性を引き戻し、選手は怒りを喉で飲み込みます。
警告後、配球は一転して“無用な刺激を避ける組み立て”へ。外角中心の攻防に見せつつ、勝負どころでは高低差で目線を外す。内外野の会話が一段と増え、守備位置の数十センチの調整が積み重なる。緊張を“戦術”に変える、プロの底力を私は目撃しました。

個人的に胸を打たれたのは、再開後に両軍の投手が“投げ急がなかった”ことです。どよめきと怒りの残響がまだ球場に漂う中で、キャッチャーは深呼吸のジェスチャーを示し、投手は首を縦に振る。観客の熱を利用して力任せに行くのではなく、むしろ一段ギアを落としてコマンドで勝負する。あの落ち着きがなければ、今日の名勝負は生まれなかったはずです。
🔵 ブルージェイズの強さと誇り
正直に言って、ブルージェイズは本当に強かったです。
- 投打ともにバランスが良く、特に守備の堅さが際立っていました。
- 攻撃ではゲレーロJr.とビシェットの存在感が抜群!
- 応援の声量はドジャースファンを上回るほど。
👑 印象的なシーン
- 4回のピンチをしのいだジェイズ投手陣にスタンド総立ち
- 試合後、ゲレーロJr.がベンチで流した“悔し涙”
→ 彼の涙は敗者のものではなく、「誇りの証」でした。
挑戦者のブルージェイズがいたからこそ、この試合は名勝負になった。
私はそう感じています。
第3章 ブルージェイズの強さ――ゲレーロJrの涙が語ったもの

この夜のブルージェイズは、本当に強かったです。打線の厚みはもちろん、守備の一歩目、走塁の判断、継投の思い切り。どれもが第7戦の基準を満たしていました。劣勢でもベンチの空気を折らせない。打席へ向かう打者の背中を、チーム全体で押し上げるムードがあったのです。
そして試合後、ゲレーロJrがダグアウトで見せた悔し涙。私は画面の前で黙祷のように目を閉じました。あの涙は、敗北の言い訳ではなく、闘い切った者だけが流せる誇りの結晶。カメラに背を向けながらも仲間の肩に手を置き、次を見据えるその姿勢に、挑戦者の矜持を見ました。彼らの強さがあったから、この試合は名勝負になったのです。来季、きっとこの経験は彼らの武器になります。
ベンチワークの巧みさも特筆でした。代走や守備固めの投入が早く、相手のベンチを常に“考えさせる”状態に置き続ける。結果だけを見れば一球、一振りの差かもしれませんが、その一球に辿り着くまでの分岐点には、無数の英断と我慢がありました。シュナイダー監督の試合後の表情には、敗者の悔しさと同時に、やり切った者の澄んだ静けさがあったと私は感じます。
🔥 山本由伸、ゼロ日登板の奇跡
前日120球を投げたばかりの山本由伸。
まさかの**連投登板(ゼロ日)**に日本中が驚きました。
「いけます。チームのために。」
—— 山本由伸
9回途中から登板し、
160km/hのストレートと落差のあるスプリットで打者を圧倒。
- 投球回:2回2/3
- 被安打:2
- 失点:0
- 奪三振:4
💎 山本のすごさ
- 前日登板にもかかわらず球威が落ちない
- 感情をコントロールし続けたメンタル
- 仲間を信じて守備を任せる落ち着き
最後の併殺を取った瞬間、
彼が胸に手を当てて一礼した姿は、まさに“侍の魂”でした。
第4章 ウィル・スミスの一振りと、見えない仕事

勝負を決定づけた一撃は、疲労と重圧をまとめて振り払うようなスイングでした。スタンドのざわめきが一瞬だけ止まり、次の瞬間に爆発する。あの空白の一拍こそ、野球の魔法。けれど捕手・ウィル・スミスの価値は一発だけでは語れません。多彩な投手陣を束ね、相手の反応を見ながらサインを微調整し、守備位置の合図を後方から統率する。投手の表情が曇ればマウンドに歩み寄り、深く頷いて背中を押す。
極限の第7戦で、彼は“時間の管理者”でもありました。テンポが落ちればあえて間を取り、相手の勢いが出れば次の配球を早める。見えないところで勝利を積み上げた“屋台骨”こそウィル・スミス。攻撃でも守備でも、彼が最後までブレずに中心にいたからこそ、チームは迷わずにいられたのだと思います。
【捕手が積んだ“見えない勝ち点”】
・間の使い分けで投手のスタミナを節約
・インサイドワークで判定の信頼を蓄積
・守備位置の微調整で長打を単打に変換
・マウンドビジットのタイミングで流れを遮断
・サインの簡素化で走者の“読み”を無効化
配球面の妙も随所に光りました。直球でストライクを取りに行くのか、初球から変化球で目線を下げるのか。相手が狙い球を決めてきたと見るや、次の打席では逆手を取る。二巡目と三巡目でまったく違う攻めを示すことで、相手の“学習”を逆利用する。スミスはその舵を切り続け、投手の個性を最大化しました。試合後のヒーローインタビューで多くを語らない寡黙さも、彼らしい“職人の背中”に見えました。
⚡ ウィル・スミスの決勝弾と捕手の献身
試合を決めたのは、ウィル・スミスの11回ホームラン!
ライトポール際に吸い込まれた打球を見て、球場が一瞬静まり、次の瞬間に爆発的な歓声!
🎯 スミスの活躍まとめ
- 打撃:決勝HRでヒーローに
- 守備:全試合マスクをかぶり、リードも完璧
- 投手を支える“縁の下の力持ち”としてMVP級の貢献
彼の配球とマウンドへの声かけがあったからこそ、
山本由伸も安心して投げられたと思います。
第5章 山本由伸、ゼロ日登板の矜持――MVPという帰結

前日の熱投から間髪入れず、再びマウンドへ。正直に言って、私は“さすがに厳しいのでは”と不安も抱えていました。しかし、初球がミットに吸い込まれた瞬間、その不安は霧のように消えます。高めの真っすぐで視線を上げ、低めのフォークで膝を折らせ、カウントが苦しければカットで芯を外す。リズムが生まれると、内野の足取りも軽くなる。球数の重みを背負いながらも、投げるたびに空気を制圧していく。
終盤最大のピンチ、併殺で締めた後に胸へ手を当てて一礼する姿に、私は何度目かの涙をこぼしました。ゼロ日登板で2イニング以上を無失点、最後を任されて試合を締め、シリーズMVP。これは偶然ではなく、覚悟と準備の結果です。短い時間に彼が示したのは、技術だけではありません。仲間を信じ、チームの明日を背負う“精神”でした。日本のエースが世界の頂で刻んだ一行は、私たちの日常にも勇気を灯してくれます。
【山本由伸・第7戦で伝わったこと(私的メモ)】
・“いけます”の一言に宿る覚悟
・球種配分よりも“ゾーンの使い分け”で勝負
・味方の守備を信じ切るテンポ
・ベンチの空気を安定させる所作
・最後の一球まで姿勢を崩さない集中
マウンドを降りた瞬間の、仲間に向けた小さなガッツポーズも忘れられません。過度に感情を爆発させないのに、全身から熱が伝わってくる。ダグアウトへ戻る際にコーチと短く言葉を交わし、次の回の準備へ無駄なく移る所作に、一流の時間術を見ました。数字に表れない球威とコマンドの“質”が、最後の数アウトを引き寄せたのだと私は確信しています。
🧠 監督・コーチ陣の采配と支え
試合を裏で支えたのは、やはり首脳陣の采配です。
👨🏫 ロバーツ監督(ドジャース)
- 山本のゼロ日登板を決断
- 継投タイミングの見極めが的確
- 試合後、涙を浮かべて選手を抱擁
🧢 シュナイダー監督(ジェイズ)
- 早めの継投策で試合をコントロール
- ベンチの温度を常に保つ采配
- 試合後「誇りに思う」とコメント
乱闘寸前の場面でも、両監督が前に出て冷静に収めたのは本当に立派でした。
おわりに――野球は、私たちに希望の形を教えてくれる
朝8:50に始まり、14時前に終わった6時間の死闘。
私は一瞬たりとも目を離せませんでした。
- ドジャースの連覇
- 山本由伸のMVP
- ゲレーロJr.の涙
この試合には、勝敗以上の“心を動かす物語”がありました。
勝者にも敗者にも、スポーツマンとしての誇りがありました。
✨ ヒロのまとめ
「野球は勝ち負けだけじゃない。
闘うすべての人が主役なんだ。」
ドジャース、世界一連覇おめでとう!
そしてブルージェイズ、本当に強かった!
この第7戦をテレビで観戦できたこと、
それ自体が私にとっての“最高のプレゼント”でした。
朝の8時50分に始まり、時計が14時に届く手前で幕を閉じたこの試合を、私は一生忘れません。強者が強者として立ち、敗者が敗者として誇りを示し、審判と首脳陣が意地と理性でゲームを守った。そこにいた全員が主役で、誰一人として“脇役”はいなかった。
ブルージェイズの圧巻の応援、ゲレーロJrの涙、死球をめぐる軋み、そしてドジャースの劇的逆転と歓喜。どの瞬間も、スポーツが私たちの心を動かす理由を思い出させてくれました。最後に、山本由伸。ゼロ日で投げ切り、MVPを手にした日本のエースに、私は心からありがとうと言いたい。あなたの一歩が、私たちの日常にも勇気を灯しました。
次にこの景色を見られるのは、いつになるでしょう。だから私は、今日の鼓動をここに書き残します。読み返すたびに、8時50分の高鳴りと、14時前の歓喜がきっと蘇るはずです。さあ、胸を張って言います。ドジャース、世界一連覇おめでとう! ブルージェイズ、あなたたちも最高に強かった! この物語を見届けられたことを、私は一生の誇りにします。

コラム:野球解説者の目線での〈頂上決戦〉─第7戦に刻まれた“野球の物語”
――解説者の眼で見る、Los Angeles Dodgers vs Toronto Blue Jays Game 7(5-4/11回)――
この試合に関して、各解説者が口を揃えるキーワードは “緊迫”、“厚み”、“ひと振りの差”でした。まさに、勝敗を分けたのはわずかな歯車のズレであり、そこに“物語性”が宿ったと言って差し支えありません。
1.まず「厚み」で勝ったドジャース
解説者はまず「ドジャースのチーム構成の厚さ」に注目しています。先発・中継ぎ・攻撃陣・守備と、どこかに“穴”があるという印象を、相手のブルージェイズにはほとんど与えませんでした。特に第7戦において重要だったのは、終盤に向けて“継投・守備対応”が一段ギアを上げたこと。ブルージェイズが4点リードを奪った段階で、多くのアナリストは「ここで阪神ならひるむ」「負けたら31年ぶりの未達」といった重圧を語っていましたが、ドジャースはその重圧を“次のアウト”に変えることで流れを引き戻しました。例えば、9回裏に追いつく場面、11回に一発を放つ場面――それらは偶然ではなく、準備と厚みの結果だったという声が多いです。ガーディアン+1
2.ブルージェイズの“誇り”と“弱点”
一方、ブルージェイズを評価する解説も「本当に強い挑戦者だった」というものです。守備範囲、走塁判断、戦術的継投――どれも一級品。しかし、「勝負の一瞬を制せなかった」ことが最後に響きました。9回表に4-3のリードを得た時点で勝利確率は90%を超えていたとも言われ(ESPN解析)、そこからの逆転を許したことが“悔し涙”の背景になったと指摘されています。ウィキペディア+1
ブルージェイズの強みとしては、応援団の熱量も挙げられます。ホームのロジャース・センターで展開された青のウェーブは“合唱の壁”と呼ばれ、相手の集中を微妙に揺さぶる効果があったと報じられています。しかし、そのノイズさえも“決勝点を奪われるまで”は勢いだった、という指摘も。「場内の雰囲気を味方にしきれなかったのが悔やまれる」と解説者は語ります。ガーディアン
3.緊迫を生んだ“死球・乱闘寸前”の場面
プロの解説者が「この試合で印象に残ったポイント」として必ず挙げるのが、4回の死球→ベンチ総出の一幕です。打者アンドレス・ヒメネスへの連続死球から、両軍ベンチが飛び出し、場内は“乱闘寸前”の緊張感に包まれました。MLB.com+1
この場面は単に怖かっただけではありません。解説者はこう解説します。
「この入り口で心を失ったチームが、あと数イニングで勝ち負けを決するわけです。冷静さを取り戻せるかどうかが、最終的な勝負に直結します。」
まさに、ドジャースがこの危機を“戦術的に受け流せた”ことが勝因の一つとして挙げられています。両監督・ベンチの落ち着きが、選手へ伝わったことの証です。
4.“ひと振り”で決まった勝負
第11回表、2アウト走者なしという場面。打席にはウィル・スミス。相手投手ショーン・ビーバーのスライダーを捉え、ライトポール際へのホームラン。解説者曰く、
「準備していた一振りが、重圧を力に変えた瞬間」True Blue LA+1
この場面を“勝負振り”と呼び、特に以下の構図が話題になりました。
- 相手の継投を見切った選択打
- 捕手との配球駆け引きの優位
- 打者自身の態度(勝負どころでの静けさ)
“ひと振り”で勝敗が決まる試合――それは確かに“野球らしさ”全開の瞬間でした。
5.日本人投手が世界一を演出した意味
そして、この試合のもう一つの大きなレイヤーとして挙げられるのが、山本由伸の存在です。前夜に120球を投げた翌日、ゼロ日でマウンドへ。2回2/3を無失点で締めてシリーズMVP。AP News+1
複数の解説で語られていたキーワードは「メンタルの強さ」と「信頼の矜持」。
「彼は疲労を理由に投げない選択もできた。だが“チームのために投げる”その姿勢が、9回以降の流れを変えた」
その言葉通り、山本の登板以降、ドジャースの流れが“守り切る”モードへ一変しました。解説者はこう結びます。
「この試合で山本は“世界一の舞台で日本人が頂点に立つ”図を描いた。そしてそれは偶然ではない」
まとめ
今回のGame 7は、単なる勝ち負け以上の“物語”を内包していました。
両チームが全力を出し尽くし、決定的な一振り・一球・一選択で勝敗が決した。緊張の連続、その裏で“厚み”や“誇り”や“矜持”が映し出されていました。
解説者たちはこの試合を「歴史に残るクラシック」「プロ野球の教科書」とまで称しています。私たち観る側としても、ただのテレビ観戦ではなく、選手・監督・ファンすべてが主役となった“ライブの証人”だったのだと思います。
この先何年経っても、今日のこの試合が語り継がれることは間違いありません。

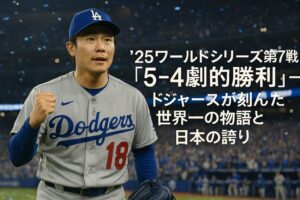

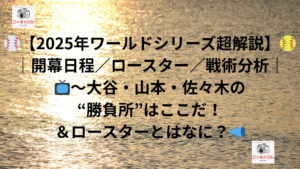
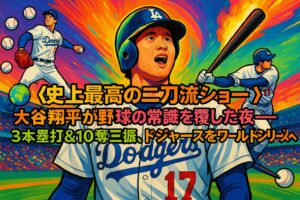
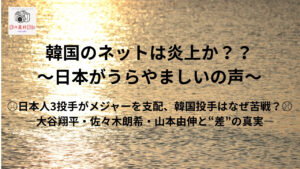
コメント欄